2025.06.30
【徹底比較】ウェビナーvsYouTube|最強の集客ツールはどっち?【OTSUNAGI株式会社 茂木優弥様】

本記事では、動画マーケティングにおける「ウェビナー」と「YouTube」それぞれの強みと活用法を比較しながら、リード獲得や商談化につなげる実践的な方法を紹介します。
お話を伺ったのは、ウェビナー専門のコンサルティング会社「OTSUNAGI株式会社」代表・茂木優弥氏。
これまでに累計200回以上の企画・登壇を手がけ、20社以上のウェビナー支援を実施。BtoB・BtoC双方の現場で成果を生み出してきた、まさにウェビナーのプロフェッショナルです。
本記事では、そんな茂木氏とともに、ウェビナーとYouTubeという2大動画チャネルの違いや活用方法を深掘りしていきます。
YouTube運用の無料相談はこちら>>
無料で資料をダウンロードする>>
そもそもウェビナーとは?YouTubeと何が違う?
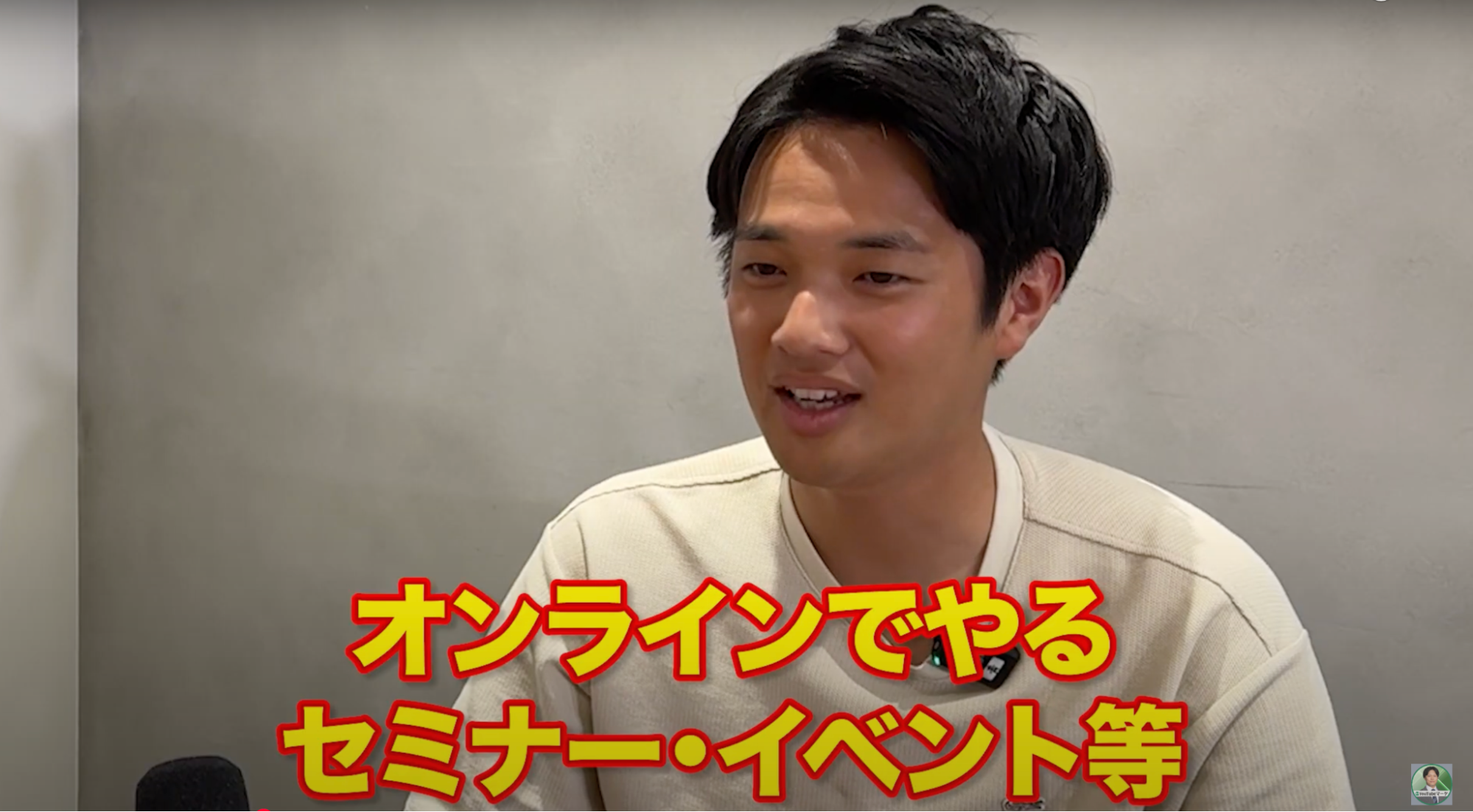
茂木さん:ウェビナーはインターネット上で実施するオンラインセミナーを指します。
鳥屋:同じ動画コンテンツでもYouTubeとはどう違うのでしょうか?
茂木さん:大きな違いは、視聴にあたって参加登録が必要な点です。これにより、参加者の基本情報や関心テーマなどの情報を取得でき、営業リードとしても活用できます。
また、ウェビナーはリアルタイムでの質疑応答やアンケートも可能で、参加者との双方向コミュニケーションがしやすいのも特徴です。
鳥屋:なるほど。YouTubeが「広く届ける」チャネルだとすれば、ウェビナーは「深く届ける」チャネルですね。
【ウェビナーvsYouTube】拡散力・集客力が高いのはどっち?
鳥屋:YouTubeでは、1本の動画が数万回以上再生されることも珍しくありません。そこから問い合わせや資料請求につながるケースもありますよね。
一方で、ウェビナーはクローズドな分、リード数が少ないという印象があります。実際のところはどうなんでしょうか?
茂木さん:たしかに、ウェビナーは集客が難しいと思われがちですが、“共催”という形式を活用すれば、かなり大規模な集客も可能です。
複数の企業が共同で開催し、それぞれの顧客リストを掛け合わせることで、単独開催よりも圧倒的に広いリーチが実現できます。イメージとしては、オンライン版の合同説明会に近いですね。
鳥屋:それなら、YouTubeに比べてリードが取れないという印象は、必ずしも正しくないんですね。
茂木さん:はい。実際に、1回の開催で500~1,000名規模の集客を実現した事例もあります。
また、事前登録制なので、参加者の基本情報が取得できる点も強みです。質の高いリードを効率よく獲得できるという点では、YouTubeにはないメリットがあります。
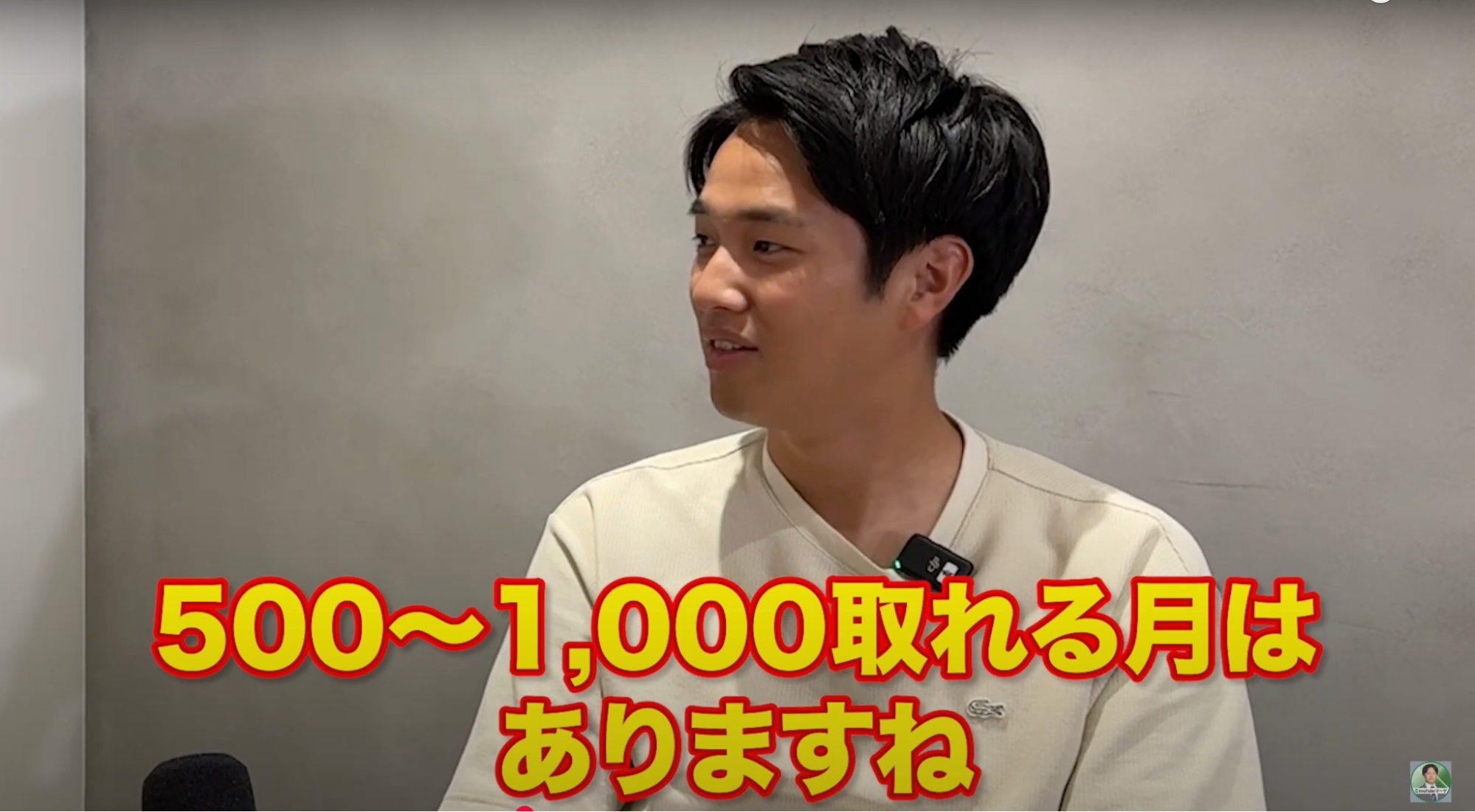
「集客失敗が怖い」は誤解!ウェビナーは“予測できる集客”が強み
鳥屋:ウェビナーは“一発勝負”という印象があり、「もし人が集まらなかったら…」という不安の声もよく聞きます。YouTubeのように、後からジワジワ再生数が伸びる構造とは違いますよね。
茂木さん:たしかにそう思われがちですが、実はウェビナーの集客はある程度予測可能なんです。
たとえば、自社のハウスリストへのメール配信やクリック率などの反応データから、どれくらいの申し込みが見込まれるかを予測できます。
加えて、SNSやメールで「このテーマのウェビナーがあったら参加したいですか?」とヒアリングすることで、需要の有無を事前に把握することも可能です。
鳥屋:なるほど、実際の数字に基づいて集客見込みを立てられるんですね。
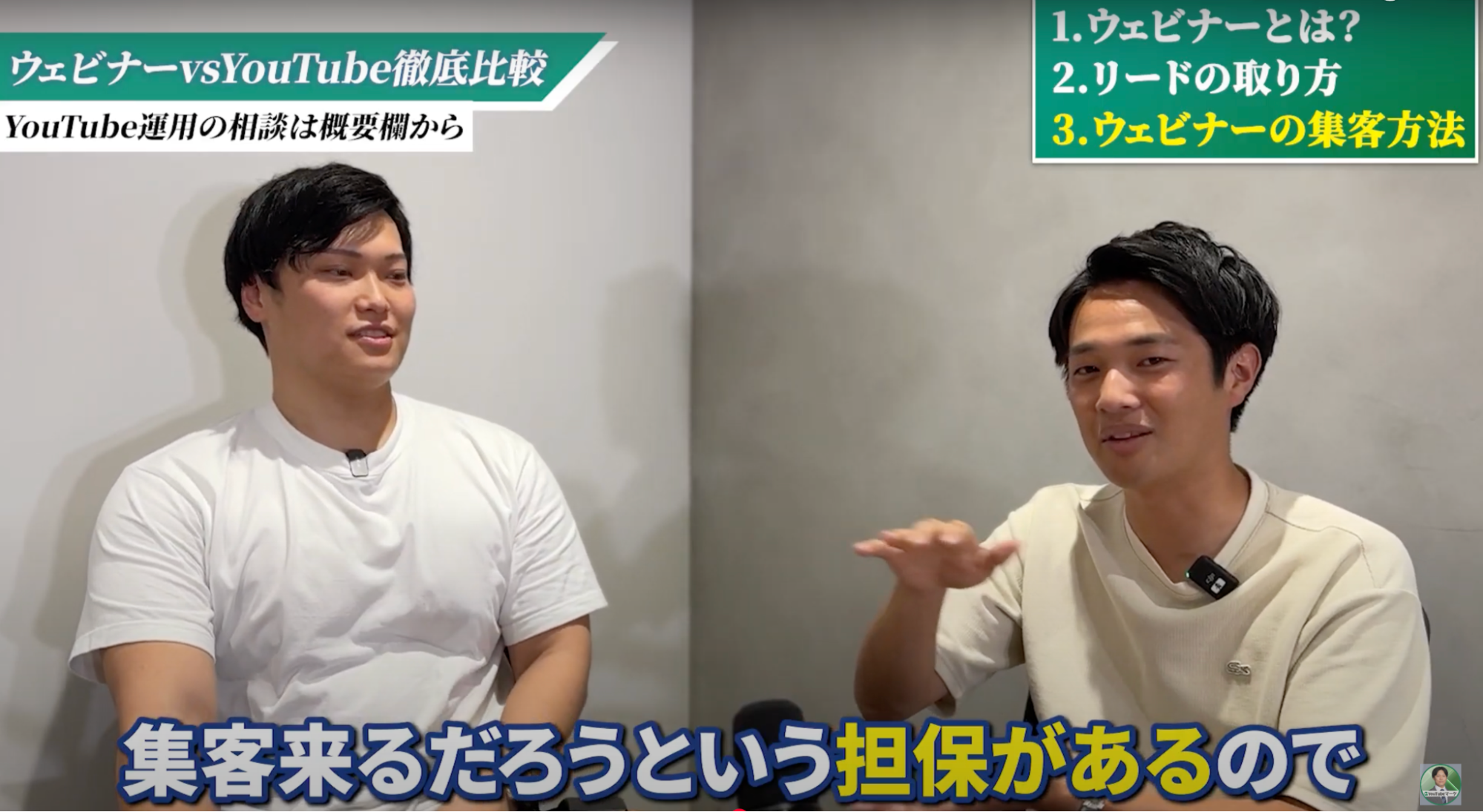
1度きりじゃない!ウェビナーは何度も使える営業資産
鳥屋:ウェビナーは、一度きりの施策と思われがちですが、実際はどうですか?
茂木さん:むしろ今では、録画ウェビナーやアーカイブの活用が主流です。ライブ後にオンデマンドで公開することで、資産として繰り返し活用できます。
鳥屋:リアルタイム配信だけが有効なわけではないというのは驚きです。実際に活用している企業は多いのでしょうか?
茂木さん:はい。弊社が2023年に行った調査によると、ウェビナー経由で月1件以上の「受注」につながっている企業は140社中48社でした。
そして、そのうちの約70〜80%が録画コンテンツを繰り返し活用しているという結果が出ています。
鳥屋:それはすごいですね。とはいえ、資料作成はやはり手間がかかる印象があります。
茂木さん:たしかに初回は一定の労力がかかります。ただ、一度しっかり作った資料は、その後も繰り返し活用できる資産になります。
録画やアーカイブにして再配信すれば、中長期的なリード獲得にも役立ちますよ。
また、同じ内容でもタイトルや見せ方を変えるだけで、違うターゲット層に“別企画”として届けることもできます。
鳥屋:中長期で見れば、初期コストに対するリターンが非常に大きいんですね。話を聞いていたら、ウェビナーにも挑戦したくなってきました。
なぜウェビナーのプロがYouTubeにも力を入れるのか?
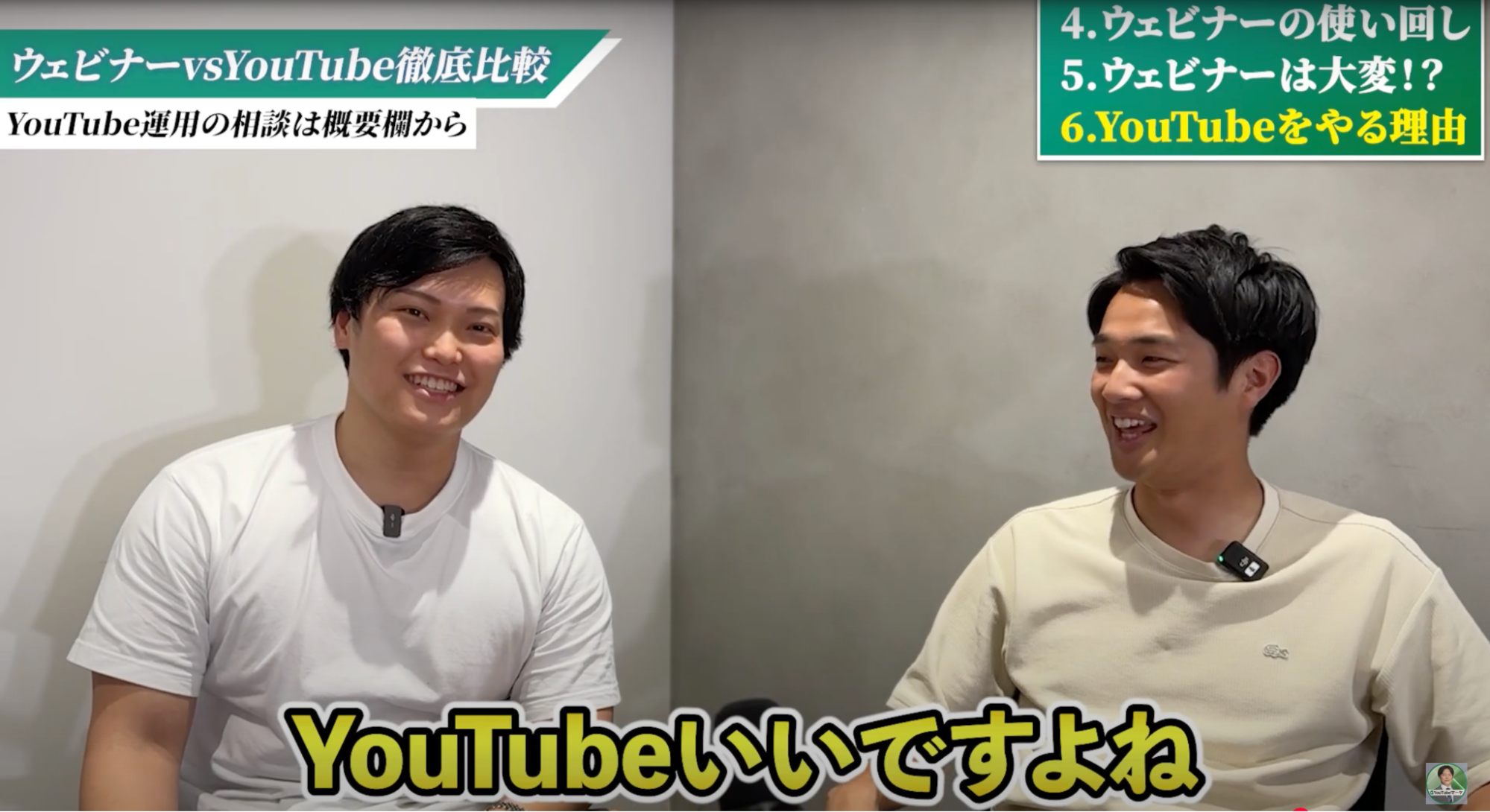
鳥屋:茂木さんはウェビナーの専門家でありながら、YouTubeにも力を入れられていますよね。その背景にはどのような理由があるのでしょうか?
茂木さん:大きな理由は、YouTubeは視聴のハードルが低いことです。事前登録や個人情報の入力が不要なので、見込み顧客が気軽にコンテンツに触れられる環境が整っています。マーケティング施策として、非常に有効だと感じています。
鳥屋:たしかに、ウェビナーよりも間口は広く感じます。実際にYouTube経由で成果につながったケースはありますか?
茂木さん:本格的な運用はまだこれからなんですが、試しに20本ほど動画を公開しただけでも複数の商談に発展したケースがあります。
また、営業メールの署名にYouTubeチャンネルのリンクを載せておくだけでも、提案前に動画を見てくださる方がいて、商談の温度感が一気に高まるケースがよくあります。
鳥屋:YouTubeは単なる集客チャネルにとどまらず、ナーチャリングや信頼構築にも有効ですね。
茂木さん:その通りです。YouTubeは「広く届ける」チャネル、ウェビナーは「深く届ける」チャネル。役割が異なるからこそ、両方を組み合わせることでマーケティングの幅が一気に広がると実感しています。
まとめ:ウェビナー×YouTubeの“合わせ技”が最強
YouTubeとウェビナーは、それぞれ「広く届ける」「深く届ける」という異なる強みを持つ動画チャネルです。
認知拡大・信頼構築にYouTube、関心度の高い見込み顧客の獲得や商談化にはウェビナーなど、この2つのチャネルをうまく組み合わせることで、BtoBマーケティングの成果は格段に高まります。
動画マーケティングに本気で取り組みたい企業様は、YouTube運用のプロフェッショナル集団・BIRDYにぜひご相談ください。戦略設計から制作・運用・内製化支援まで、実戦ベースでご支援いたします。
YouTubeの運用代行・コンサルティングはBIRDYにお任せください!
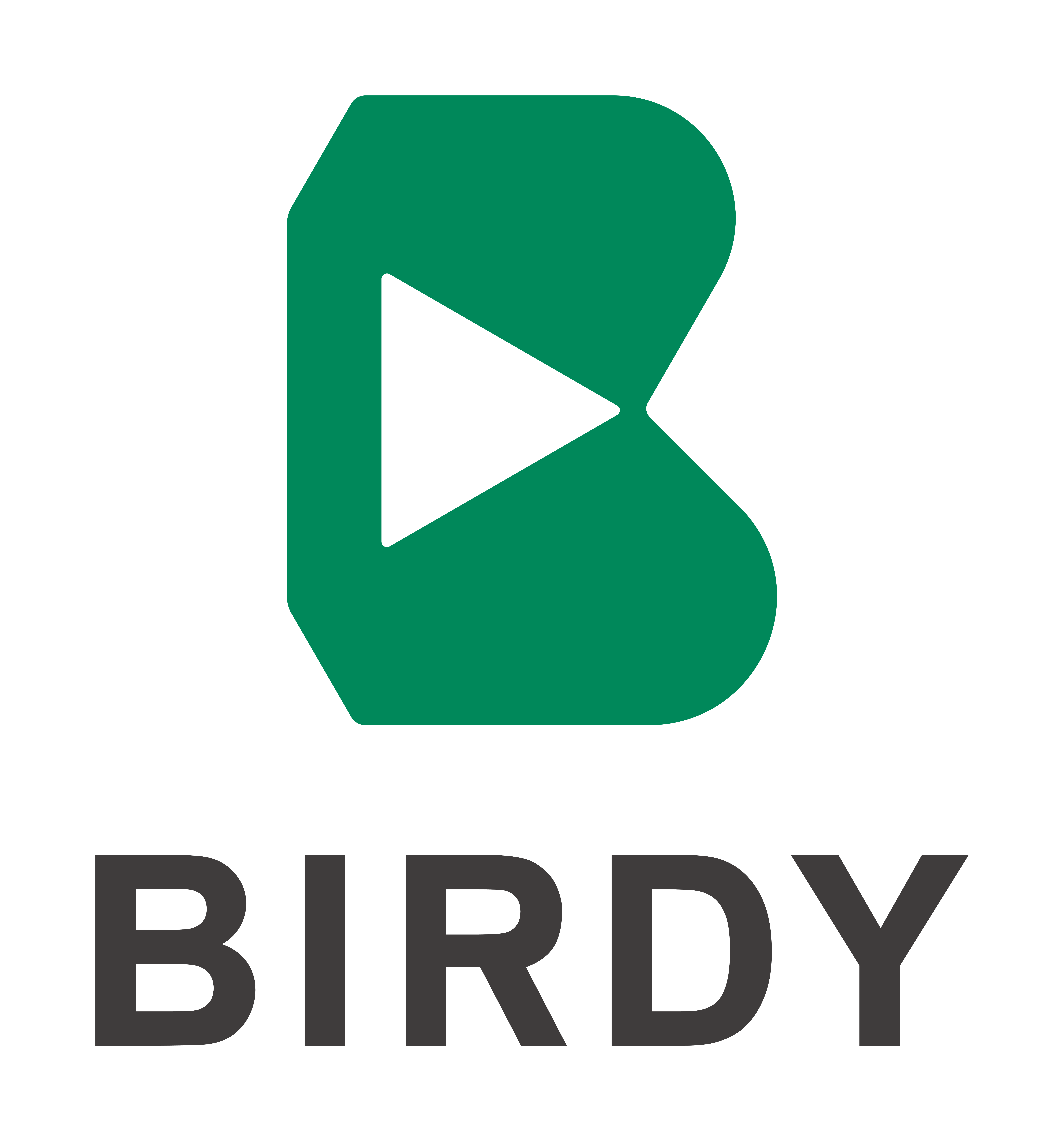
株式会社BIRDY(バーディ)は、東京都新宿区を拠点に活動する企業専門のYouTube運用代行・動画制作・コンサルティング会社です。
戦略設計から法人チャンネル立ち上げ、撮影・編集、内製化支援まで一気通貫で対応できる日本でも数少ないパートナーとして、上場企業複数社を含め、累計120社以上のYouTube支援・10000本以上の動画を企画・制作してきました。
代表の鳥屋自身が実際に運用してきたYouTubeチャンネルの知見を活かし、机上の理論ではなく“実戦ベース”で成果を出せるサポートを提供。ビジネス系チャンネル・法人チャンネルのノウハウは日本トップクラスです。マーケティング×制作の両軸から企業YouTubeを成功へと導きます。
「YouTubeを活用して集客・採用・ブランディングを強化したい」という企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
毎月10社限定
YouTube運用のご相談、無料で受付中
電話でのお問い合わせはここをクリック ▶︎
公式LINEでのお問い合わせはここをクリック ▶︎